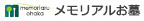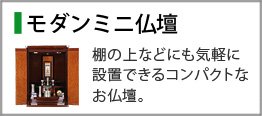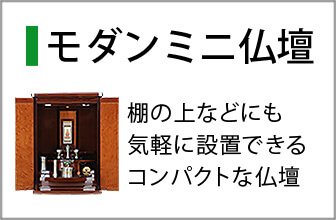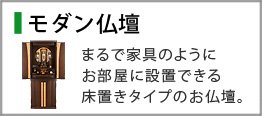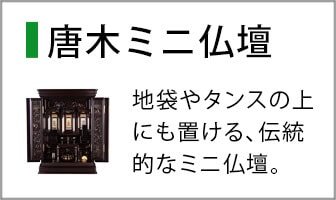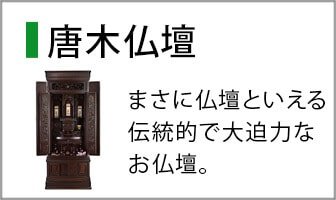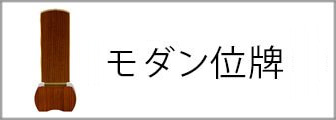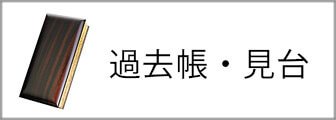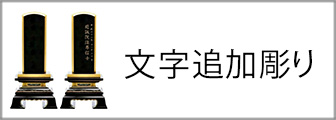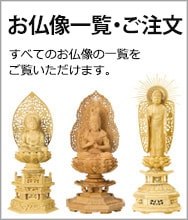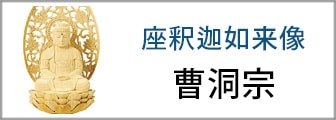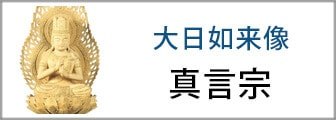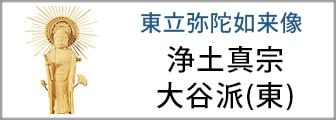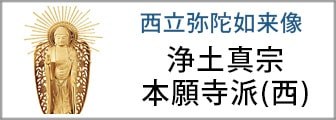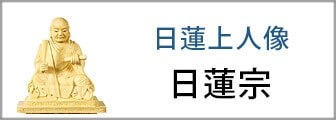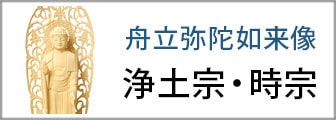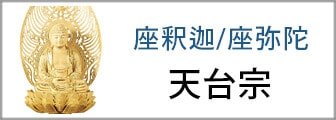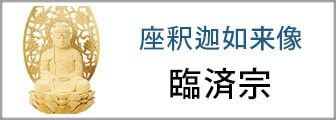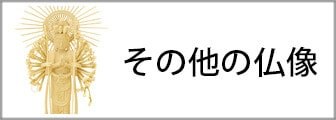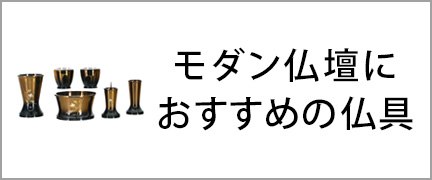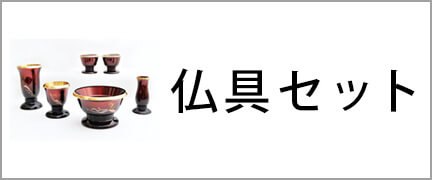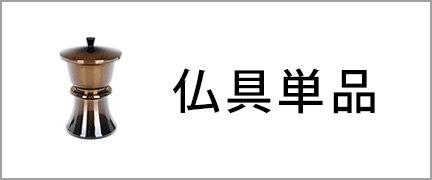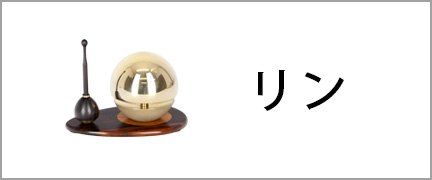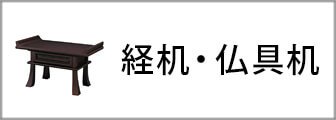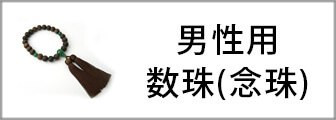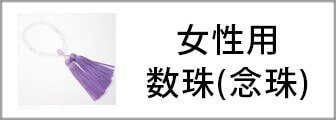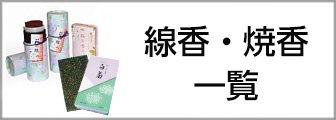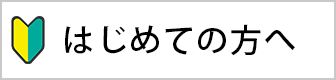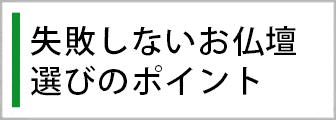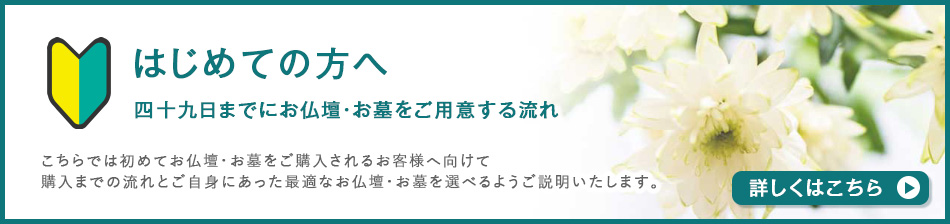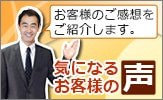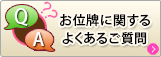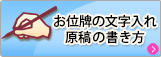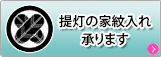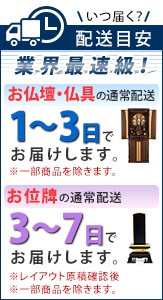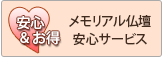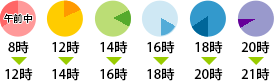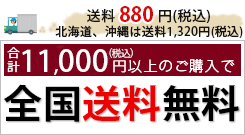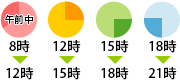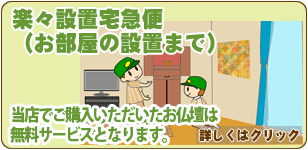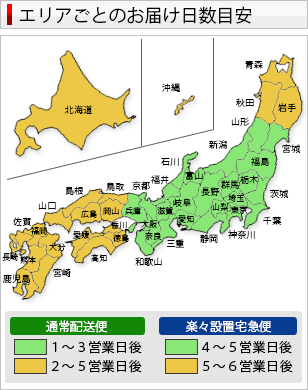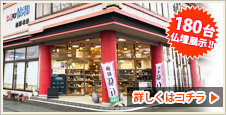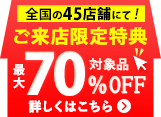位牌の選び方 【更新日】
ただしい位牌の置き方と浄土真宗の過去帳の置き方

位牌はご先祖や故人の霊魂が宿っているとされています。
仏壇に位牌を祀るときに正しい置き方を知らないと、ご先祖に対して失礼になるかもしれません。
位牌を移動する時の扱いにも、充分な注意が必要です。
浄土真宗では仏壇に位牌を置かないといいますが、その場合は亡くなった方の戒名(法名・法号)や没年月日などはどこに記すのでしょうか。
ここでは、位牌を仏壇に置くときの手順や注意点、位牌が複数あるときの置き方やまとめ方、更には、位牌を必要としない浄土真宗における法名軸や過去帳の置き方などについてご紹介します。
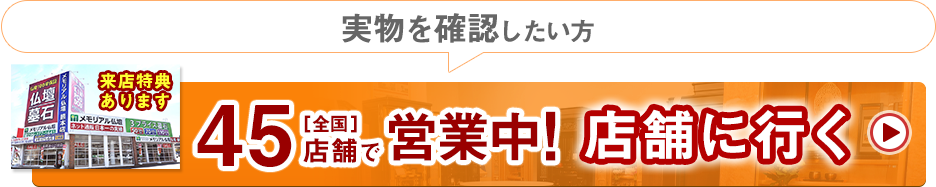
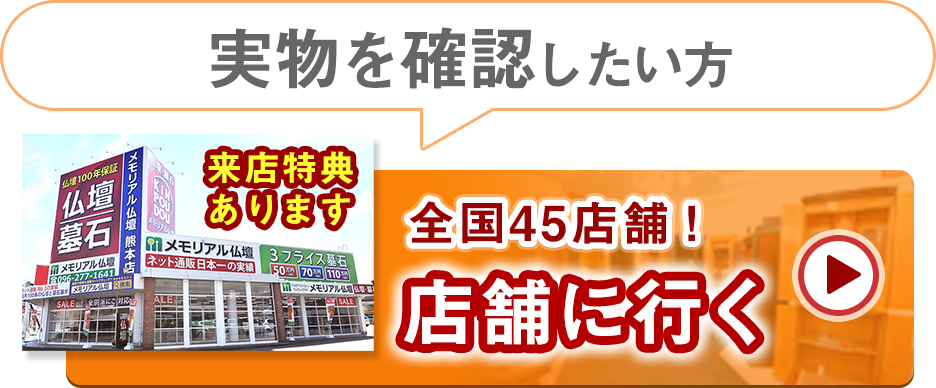

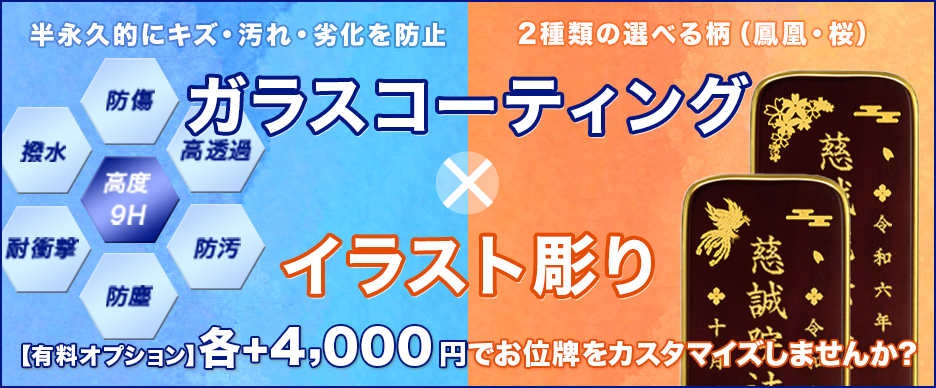
目次
位牌の置き方の前に本位牌の意味や種類について知りましょう

位牌の役割
位牌とは亡くなった方の戒名(法号)などが記された木牌を指し、そこには故人の霊魂が宿っていると考えられています。
位牌の発祥は中国と言われており、鎌倉時代から日本で使われるようになったといわれています。
位牌にはその役割によって、葬儀のときに使われる白木の位牌や、四十九日のあとに使われる本位牌、寺院の位牌堂でつかわれる寺院位牌などがあります。
白木位牌から本位牌へ
多くの人が位牌といわれてイメージする「本位牌」には、戒名や没年月日、俗名や行年(享年)を記します。
この本位牌は、四十九日までに準備しておくのが一般的です。
四十九日には、亡くなった方の霊の行き先が決まるとされていて、この日を境に仮の位牌である白木位牌から本位牌に替える必要があるためです。
位牌の種類
おそらく最もよく目にするのは、黒くて光沢のある表面に金粉や金箔などが施された「塗位牌」でしょう。
黒檀などの高級木材でつくられた「唐木位牌(からきいはい)」も多く使われています。
また最近では、モダン位牌といってクリスタルの透明な位牌や、カラフルな色をつかった位牌も増えています。
位牌は宗派によっての厳密な決まりがあるわけではないので、様々な種類の中から故人のイメージやご家族の好みに合わせて選ぶといいでしょう。

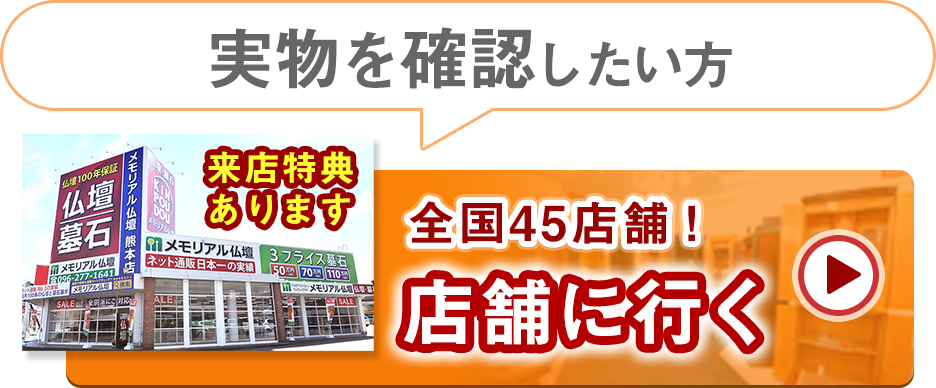

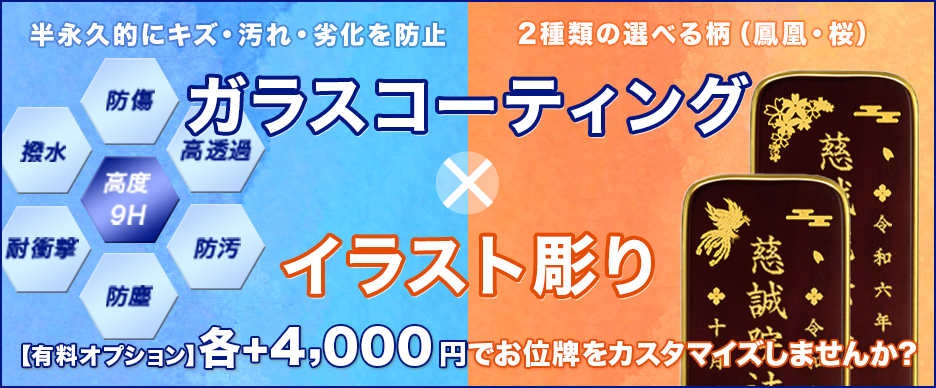
仏壇内での位牌の置き方ではご本尊や先祖の位牌への配慮が必要です

では、仏壇内で位牌はどのように置けばいいのでしょうか。
故人の魂の依り代(よりしろ)とも呼ばれるお位牌ですから、置き方には気を遣わなければいけません。
ご本尊と位牌
ここで重要なのは、仏壇の中心はあくまでも仏像や掛け軸などのご本尊だということです。
そのため、位牌はご本尊の一段下の右側に置くというのが基本となります。
仏壇によっては、ご本尊が安置された上段と位牌を置いた段の差があまりない場合があります。
位牌がご本尊よりも高い位置にきてはいけないので、大きい位牌の場合は3段目に置いても良いかもしれません。

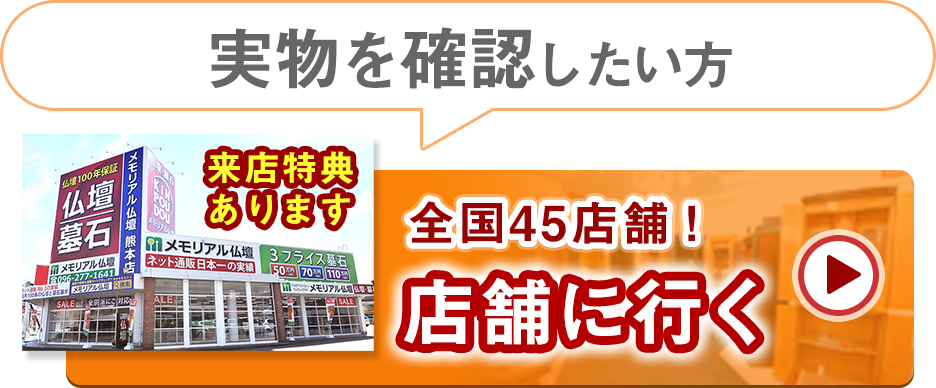

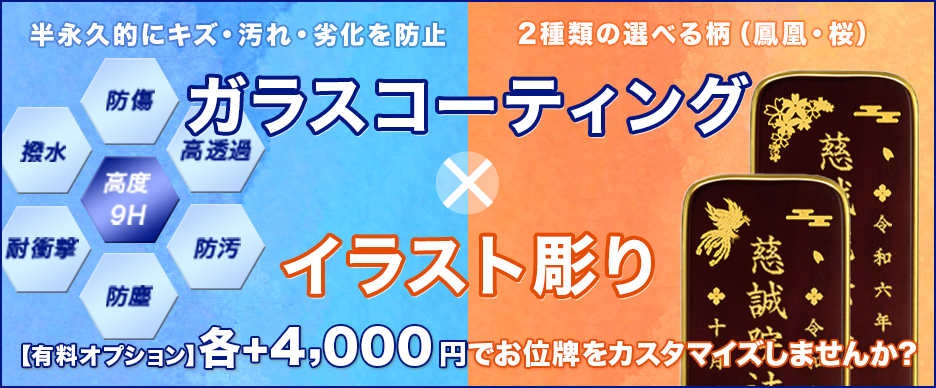
複数の位牌の配置
位牌が1つだけの場合は、ご本尊の下の段の右側に置きますが、仏壇に複数の位牌があるときの置き方は、その配置が大切になります。
ご本尊が安置された段の下の段に位牌を置いていきますが、まずはご先祖の方々の位牌を先に安置する必要があります。
並べる順位ですが、亡くなった順番ではなく世代の古い順番から先に並べるのが基本です。
最も世代の古い位牌を最上位である右側に置き、その後は右から左に世代の古い順に置いていきます。
その時には位牌でご本尊が隠れないように注意しましょう。
その段に置ききれなくなったら、次は1段下がって「右側から左側へ」という順番で安置していくのが基本の置き方です。
また、夫婦の位牌の置き方は、夫の位牌を右に置き、妻の位牌を左に置くという配置になります。
位牌は置き方だけではなく移動にも注意が必要です

購入したばかりで仏壇に安置する前の位牌であれば、単体で持ち歩いても問題ありませんが、いったん仏壇に置いた位牌を移動させる時には、そのための儀式が必要です。
位牌の魂入れと魂抜き
引っ越しなどの理由で位牌を家の外に持ち出す場合は、「魂入れ」や「魂抜き」などの儀式が必要です。
魂入れとは、位牌へ故人の魂を込めることで、「魂抜き」とは位牌から故人の魂を一時的に抜く儀式のことです。
位牌は故人の霊魂が宿った状態で、外で移動させてはいけません。
位牌を家の中で移動させる場合
同じ家の中で仏壇を別室に移動する際には、位牌も移動させなければいけません。
位牌を仏壇の中に安置している場合は、仏壇ごと移動するのが基本です。
仏壇から位牌だけを取り出して移動するのは避けるようにしましょう。
浄土真宗では位牌は必要ありません

浄土真宗と位牌
故人の戒名(法号)が書かれている「位牌」ですが、浄土真宗では位牌を用いません。
その理由は多くの宗派と浄土真宗の考えの差にあります。
多くの宗派では、亡くなった方は戒名を授かったあとに、あの世で仏の弟子となって修行に励み、成仏すると考えられています。その故人の修業を励まし祈るために、位牌はつくられているのです。
しかし、浄土真宗では仏の弟子にならずに、阿弥陀如来を信じていれば誰でも仏になれるとしています。
そのため、故人が成仏できるように祈るための位牌が必要ないのです。
位牌を必要としない浄土真宗では、仏壇にご先祖や故人の名前を残すために「法名軸」や「過去帳」を用います。
過去帳や法名軸について
過去帳(かこちょう)とは、簡単にいうと仏壇に保管しておく家族の系譜のことで、他の宗派でも使用されるものです。
代々の亡くなった方の法名(戒名)や俗名、享年などが記されているので、過去帳を調べれば、各家の先祖代々の家系図が分かります。
過去帳は普段は引き出しの中などにしまっておく方もいますが、仏壇に置く場合は、見台(けんだい)と呼ばれる台座の上にのせて、仏壇の右側に置くのが一般的です。
浄土真宗では「法名軸(ほうみょうじく)を使用しますが、こちらは故人の没年月日や法名を記した掛け軸のことです。
浄土真宗では戒名ではなく法名を使うので、この名前で呼ばれます。
基本的にお仏壇の内部の側面に掛けられます。

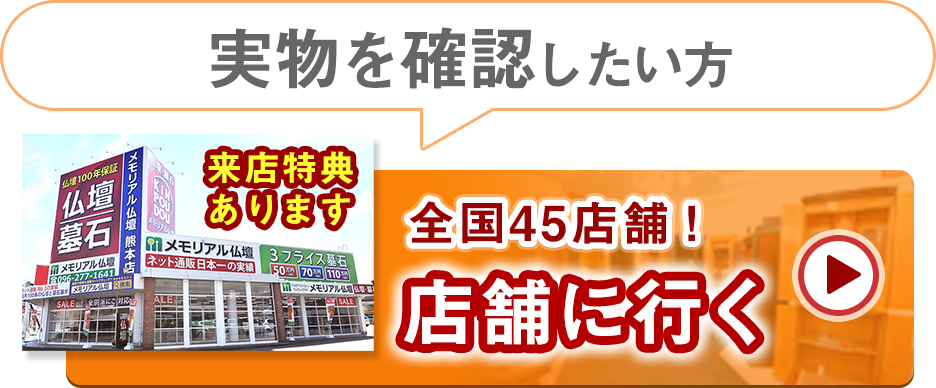

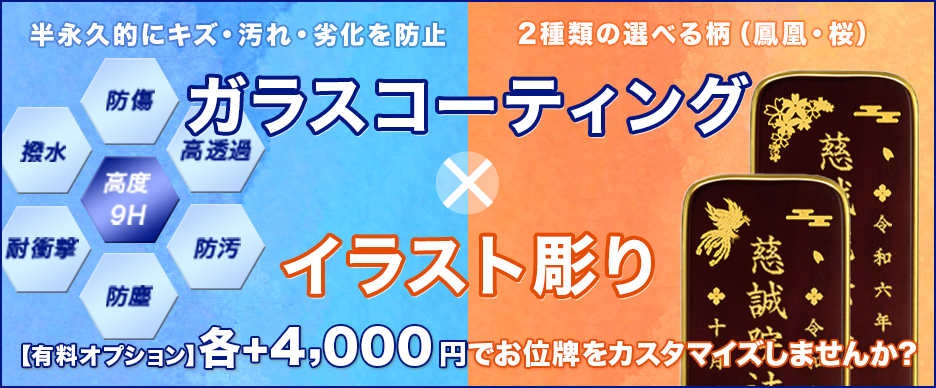
浄土真宗でも位牌を祀ります
基本的には位牌を使わない浄土真宗ですが、「浄土真宗だからといって位牌は絶対に作らない」というわけでもありません。
日本の一般家庭の仏壇では昔から位牌を祀って先祖供養をしてきました。
そのため「浄土真宗ではあるが位牌がないと不安」という方もおり、浄土真宗であってもお寺様によっては位牌の準備を許可することがあります。
位牌の選び方は自由ですが、その置き方には充分な注意が必要です。
しかし宗派や地域によっても作法が変わることがあるので、細かい点が気になる場合はお寺様へ相談するといいでしょう。
位牌は故人の分身ともいえるものですから、正しい置き方や扱い方を覚えて大切なご先祖や故人をしっかり供養できるようにしましょう。