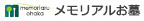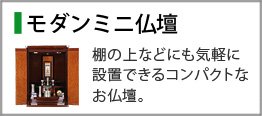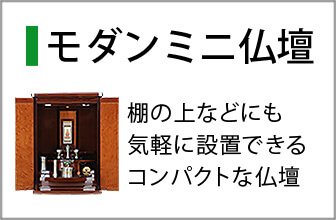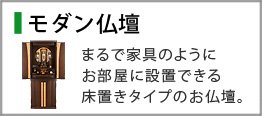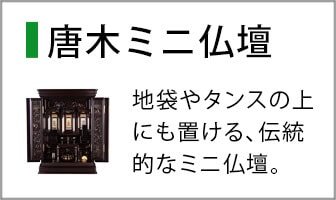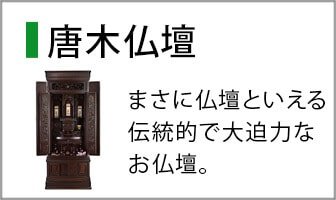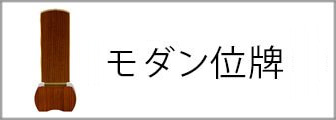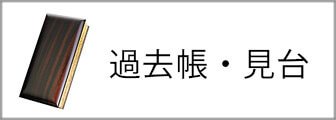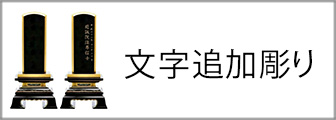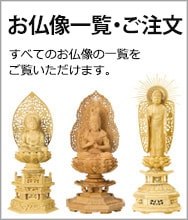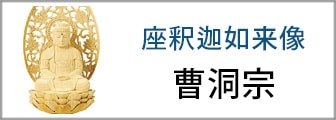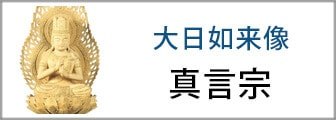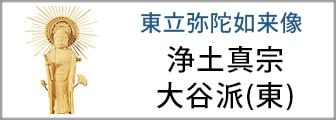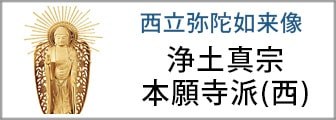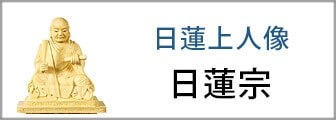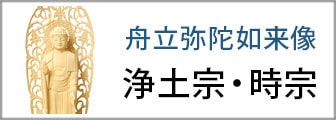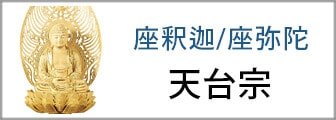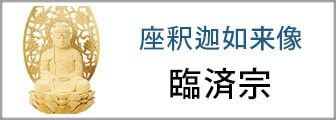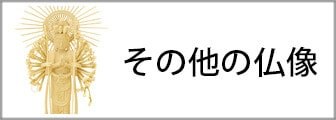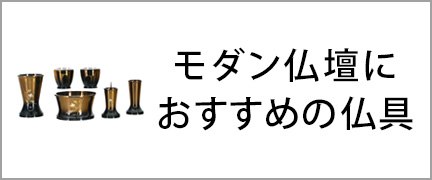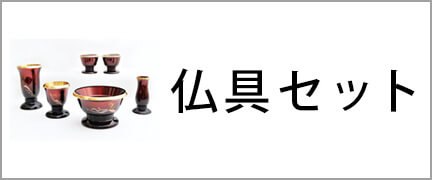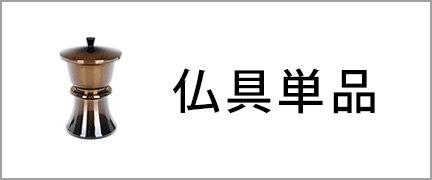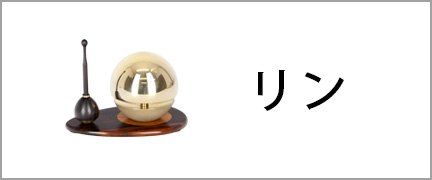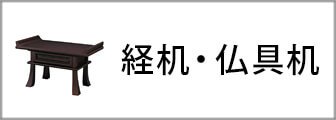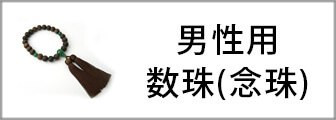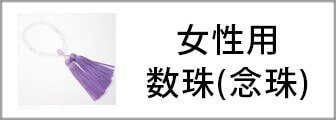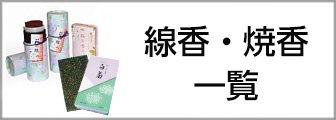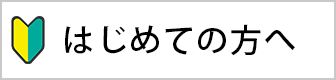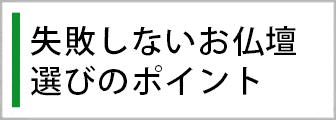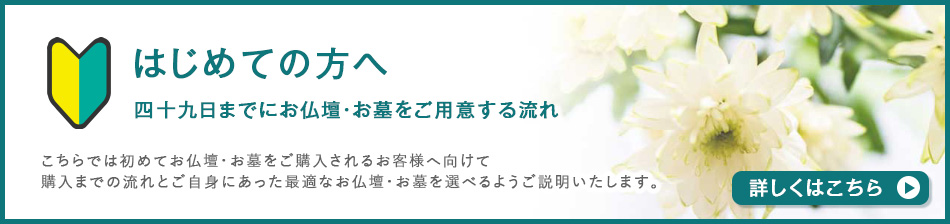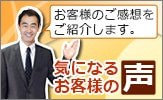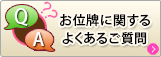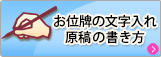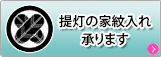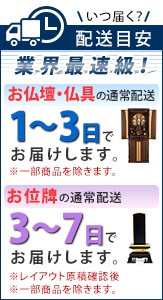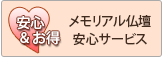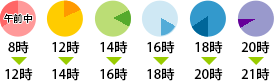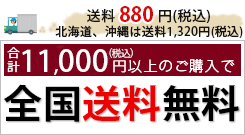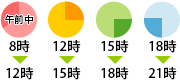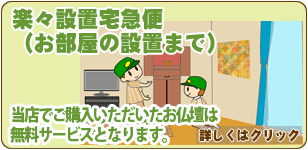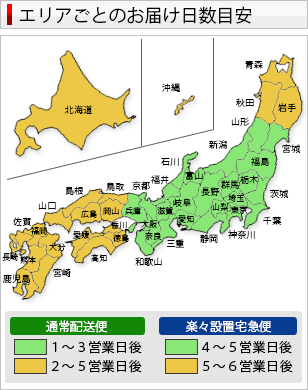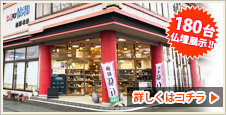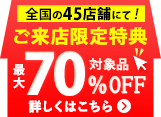仏具の選び方 【更新日】
仏具の種類は豊富にありますが、ご本尊、位牌、基本の供養具があれば大丈夫です

仏具には非常に多くの種類があります。
仏事に不慣れだと見ても何に使うものなのかさえ分からない仏具もあると思います。
たとえ仏壇のある家庭で育った方でも、ご自分の宗派で使わない仏具の種類に関しては疎いのではないでしょうか。
数ある仏具の種類の中でもせめて代表的なものの役割を知っておけば、仏具を購入する際にも戸惑わなくて済みますよね。
仏具は宗派や地域によっての決まり事があるので、購入する前に菩提寺などに確認しておいた方がいいでしょう。
ここでは代表的な仏具の種類のそれぞれの役割、そして選ぶポイントをご紹介します。
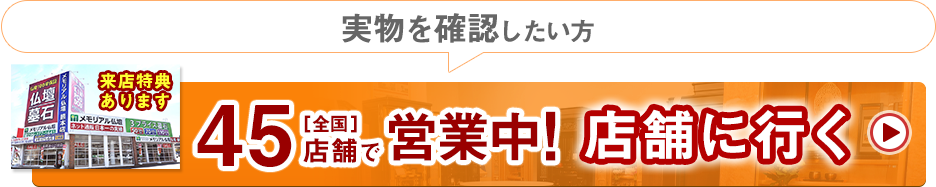
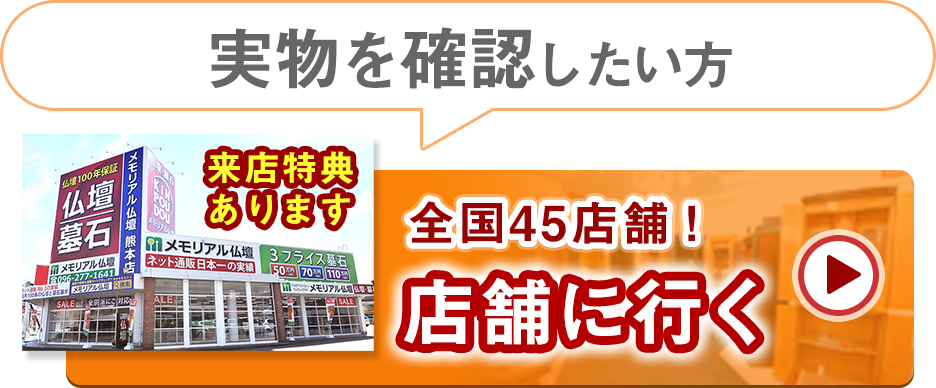
目次
仏具の種類は数あれど、ご本尊がなければ始まりません

寺院を模した仏壇にはご本尊を安置します。
ご本尊として祀る仏像や掛け軸は宗派によって異なります。
ご本尊の掛け軸は裏に印が入ったものを本山から購入しなければいけないという厳しいお寺もあるので、事前に確認は必要です。
仏像
仏像には色々な素材のものがありますが、ご家庭の仏壇には白木や柘植などで使った木彫仏像が一般的です。
仏像は仏壇中央の須弥壇に安置し、両脇に宗派で定められた祖師像(そしぞう)を祀るのが正式です。
掛け軸
掛け軸をご本尊とする場合は須弥壇中央にご本尊、左右に「脇掛(わきがけ)」と呼ばれる掛け軸を掛けるのが正式な祀り方です。
ご本尊を選ぶ時は、宗派や仏壇内部のサイズに合わせて選ぶことが肝心です。
購入したご本尊は、菩提寺で魂入れをしていただいてから仏壇に安置します。

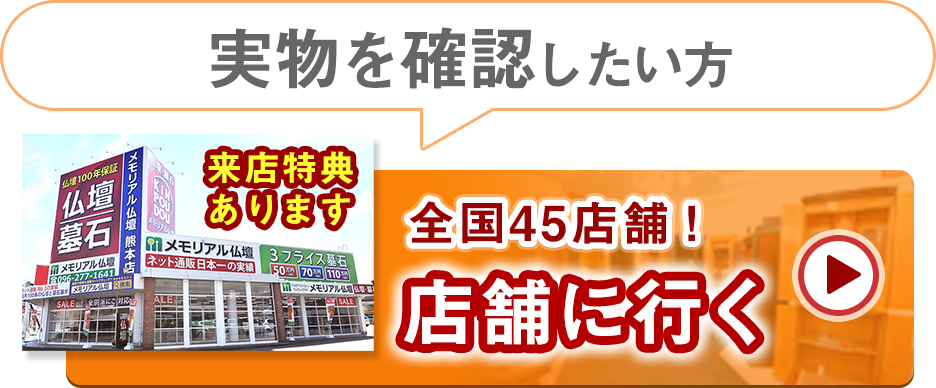
ご先祖様や故人を祀る仏具の種類を「位牌」と言います

仏壇の中央にはご本尊が隠れない形で、ご先祖様や故人を祀る位牌なども祀ります。
位牌(いはい)
位牌は故人の俗名や戒名が記された木片で、故人の魂がこもった分身とされます。
購入した位牌は菩提寺での開眼供養が必要です。
法名軸(ほうみょうじく)
浄土真宗系の多くの宗派では位牌を用いず、仏壇の内部の両側面に法名軸(ほうみょうじく)を掛けます。
法名軸とは亡くなった故人の死亡年月日と法名(戒名)、または一族の法名が記された掛軸です。
過去帳(かこちょう)
過去帳には故人の俗名(生前の名前)、戒名(法名、法号)、亡くなられた年月日、年齢、続柄などを書き記します。
寺院にある檀家全体の帳面とは別に、ご家庭の仏壇には先祖代々の故人の過去帳を「見台」に載せて安置します。

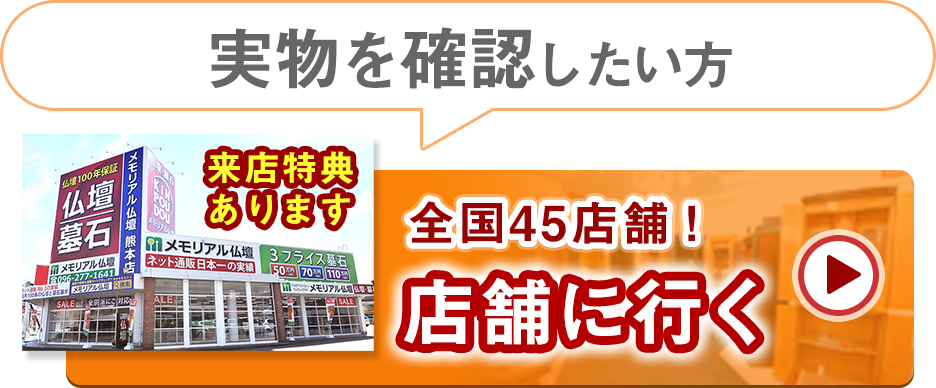
供養具の基本となる仏具の種類は「三具足(みつぐそく)」とリンです

供養具を選ぶポイント
仏壇に祀ったご本尊やご先祖様は様々な仏具を使って供養します。
供養具は宗派によって使う仏具や個数などが異なり、特に浄土真宗では本願寺派(西)では黒仏具、大谷派(東)では金仏具を使います。
真宗大谷派では鶴と亀のデザインが施された専用の仏具もあります。
浄土真宗系でない場合は、真宗専用の金色の仏具を選ばなければ問題ありません。
その上で仏壇タイプや供養スペースに合わせた大きさ、色、素材、デザインの仏具を選びましょう。小まめに洗う花立、茶湯器、仏飯器などは、お手入れが楽な素材や形状のものをお勧めします。
三具足
全ての宗派において最低限必要な供養具を三具足(みつぐそく)と呼びます。
花立て
仏花を入れて「花供養」として仏壇に供えます。
仏花は故人やご先祖様の霊を花の姿や香りで供養するためのものですが、お供えしている私達の心も穏やかにしてくれます。
香炉
中に線香を入れて「香供養」に使います。
線香の香煙は仏様の食事となるだけではなく、場や供養している者の心身の穢れを清めてくれます。
浄土真宗以外の宗派では「前香炉」、真宗本願寺派では「玉香炉」、大谷派では「透かし香炉」を使うのが一般的です。
ローソク立て
ローソクを立てて「灯り供養」に使います。
灯された火は闇を明るく照らし、故人や私達を導いてくれます。
浄土真宗では「輪灯(りんとう)」が使われます。
法事や命日など正式な場では、花立と火立を1対ずつ使って五具足で供養します。

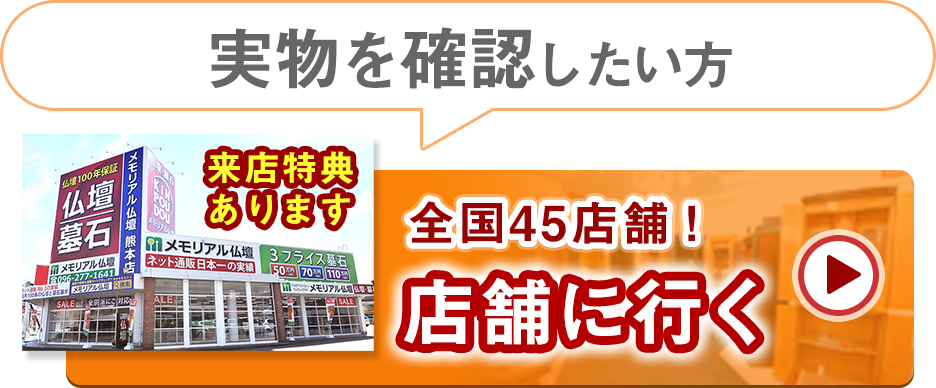
リン
全ての宗派において重要な仏具とされる梵音具(ぼんおんぐ)で「おりん」とも呼ばれます。
本来はお経の開始や終わりの合図や読経の調子をとるために使う物ですが、ご家庭では仏壇に手を合わせる時に鳴らして使う事が多いです。
仏具の種類のうち「五供(花・香り・灯り・お水・ご飯)」に使う供養具

ご先祖様や故人を供養する「花・香り・灯り・浄水(水・お茶)・飮食(ご飯)」のことを「五供(ごくう)」と言います。
五供に使う基本仏具は、前述の花立て、香炉、ローソク立ての「三具足(五具足)」に茶湯器、仏飯器を合わせた5つです。
茶湯器(茶器)
仏様の乾きを癒すために浄水(水やお茶)を入れる器で「湯茶器(ゆちゃき)」や「湯呑(ゆのみ)」とも呼ばれます。
通常は1つですが正式な場では3つ使う場合もあります。
浄土真宗では、極楽浄土には「八功徳水(はっくどくすい)」が溢れていて喉が渇くことがないと考えられているので浄水供養はしません。
仏飯器(仏器)
仏様の空腹を満たすためのご飯を入れる器です。
真宗大谷派では「仏器」と呼びます。
浄土真宗では通常は3つ、正式な場では4つ、それ以外の宗派では通常時は1つ、正式な時には2つ使用するのが一般的です。
日々の供養をサポートする種類の仏具

前述の基本供養具の他に以下のような種類の仏具を揃えておけば、日々の供養がスムーズに行えます。
線香差し(線香立て)
線香差しは仏前に供えるお線香を立てて入れておくための器で、通常仏壇の上の香炉の近くに置かれます。
マッチ消し
仏前では手で扇いで火を消すのが基本ですが、マッチ消しがあれば簡単安全に火が消せます。
マッチの燃えカスもマッチ消しに入れましょう。
仏器膳(仏器台)
茶湯器や仏飯器をのせて、一段高くして仏様にお供えするためのお膳です。
浄土真宗では「仏器台」を使います。

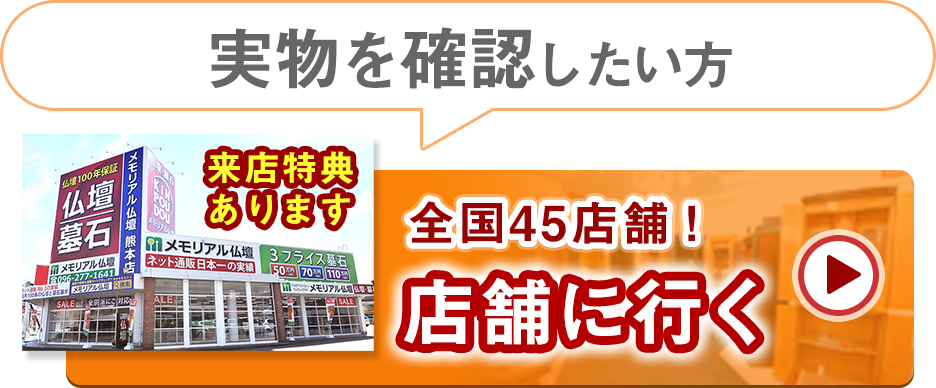
高月
お菓子や餅、果物などを供えるための仏具で「高杯」や「供物台」とも呼ばれます。
脚を高くして仏様を敬う心を表します。
浄土真宗では「供花(きょうか・くげ)」を使います。
段盛(だんもり)
数段ある供物台で使い方は高月と同じです。
主に浄土真宗で仏壇にお供えのお菓子などを供える際に用いられます。
仏壇の供養スペースが限られている場合は、日々の供養で仏器膳、高月や段盛を使うのは難しいと思います。
法事など特別な日には仏壇前に供養台を設置して、その上に置くことになります。
法事や命日など特別な時に使う種類の仏具

法事などの正式な場や命日、盆正月には特別な種類の仏具を使って盛大に供養します。
仏壇に置ききれない仏具や供養品は、仏壇の前に設置した卓や供養台の上に置きます。
仏膳(ぶつぜん)・霊供膳(れいぐぜん)
法事や命日の時に精進料理を供えるお膳セットで「親椀(ご飯)、汁椀(みそ汁等)、平椀(煮込み物)、壷椀(煮物やゴマ和え)、高皿(漬物)、箸」を入れてお供えします。
焼香盆
焼香の時に香炉や香盒(こうごう)を置くためのお盆です。
自宅での法要では部屋の広さによって、立ち上がって焼香をする脚付きタイプか、座ったまま廻して焼香を行うお盆タイプのどちらかを選びます。
切手盆・長手盆
金封やご祝儀などを贈る際に必要な黒塗りのお盆で、お葬式や法事で使う場合にはお坊さんにお布施を渡す時に使用します。
仏具の種類はとても豊富なので、初めて仏壇を購入する場合はどこまでの仏具を揃えたらいいのか非常に悩むところです。
まずは宗派に合ったご本尊、位牌から、そして日々の供養が始められるように三具足など最低限の仏具とリンがあれば大丈夫でしょう。
その後にご自分の供養スタイルやスペース、予算に合わせて少しずつ仏具の種類を増やしていければ、快適な仏壇供養ができることでしょう。